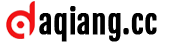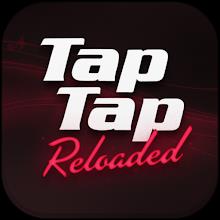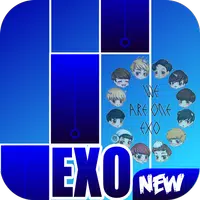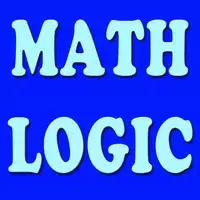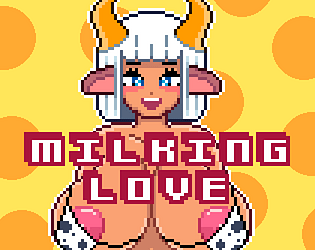Taikoドラムの世界を探る: 日本のパーカッションを深く掘り下げる
Taiko (太鼓) はさまざまな和太鼓を含み、日本の音楽遺産において重要な位置を占めています。 「Taiko」という用語は日本語では広範にあらゆる太鼓を指しますが、国際的には特に和太鼓として知られるさまざまな和太鼓と、組太鼓と呼ばれるアンサンブル太鼓のスタイルを指します。ドラムセット」)。 Taiko ドラムの細心の注意を払った製作は、メーカーによって異なりますが、使用される技術に応じて、ドラム本体とスキンの両方を準備するのに数年かかる場合があります。
日本の神話に根ざしたTaikoの歴史的存在は、早くも西暦6世紀に韓国と中国の文化交流を介して日本に導入されたことを示唆する記録によって証明されています。 興味深いことに、いくつかの Taiko デザインはインドの楽器に似ています。 古墳時代(6世紀)の考古学的発見は、この時代の日本におけるTaikoの存在をさらに確固たるものとしています。 歴史を通じて彼らの役割は多岐にわたり、コミュニケーション、軍事用途、演劇の伴奏、宗教儀式、祭り、現代のコンサートパフォーマンスなど多岐にわたります。 さらに、Taikoは国内外の少数派の社会運動において重要な役割を果たしてきました。
さまざまな太鼓を組み合わせて演奏するアンサンブルを特徴とする組太鼓は、小口大八の先駆的な活動のおかげで 1951 年に誕生し、鼓童などの有名なグループとともに繁栄し続けています。 八丈太鼓のような他の独特のスタイルは、特定の日本のコミュニティ内で発展しました。 組太鼓の世界的な広がりは否定できず、日本、米国、オーストラリア、カナダ、ヨーロッパ、台湾、ブラジルにまたがる活発な演奏グループが活動しています。 Taiko パフォーマンスの芸術には、リズミカルな正確さ、形式的な構造、スティックテクニック、伝統的な衣装、使用される特定の楽器など、多数の要素が含まれます。 アンサンブルには、通常、さまざまな樽型の長胴太鼓と小さな締太鼓が使用されます。 多くのグループは、ボーカル、弦楽器、木管楽器を取り入れてパフォーマンスを強化しています。